民族薬物資料館について
目的
世界の伝統薬物と民間薬の叡智を集積
世界各国の諸民族が伝統的に用いている薬物を民族薬物または伝統薬物と称します。 これらは各民族が生み出した文化遺産の一つであり、その民族に役立つのみならず、広く現代医療に貢献できる可能性を含んでいます。事実、欧米諸国では代替医療(相補医療)として世界の伝統医学並びに民族薬物が応用され始めています。これらの民族薬物はすべてが天然物に由来する「生薬」であり、したがって種々の品質のものが存在します。その基源(原植物と用部)は流動的であり、歴史を通じて、また各国各地で異なることもあり、異物同名品が存在することになります。
これらは各民族が生み出した文化遺産の一つであり、その民族に役立つのみならず、広く現代医療に貢献できる可能性を含んでいます。事実、欧米諸国では代替医療(相補医療)として世界の伝統医学並びに民族薬物が応用され始めています。これらの民族薬物はすべてが天然物に由来する「生薬」であり、したがって種々の品質のものが存在します。その基源(原植物と用部)は流動的であり、歴史を通じて、また各国各地で異なることもあり、異物同名品が存在することになります。
富山大学和漢医薬学総合研究所民族薬物資料館には日本漢方、中国医学、インド医学で用いられる生薬を中心として30,000点余の生薬標本が保存・展示されています。これらは、半世紀にわたり蒐集された各医学の代表的な生薬であり、また異物同名品も数多くあります。さらに、当研究所で行われた各種研究の材料生薬も保管されています。保有生薬数は日本第1位であり、教育研究用の生薬資料として高い評価を受けています。
世界の諸民族の伝統薬物を蒐集、保存、展示するとともに、それらの学術情報を収載したデータベースを構築し、伝統薬物に関する共同研究を推進して参ります。
沿革
| 昭和48年10月 (1973) |
富山大学薬学部附属和漢薬研究施設化学応用部門の増設に伴い生薬標本室を増設. 同研究施設資源開発部門で管理. |
|---|---|
| 昭和49年 6月 (1974) |
富山大学附置和漢薬研究所設置.生薬標本室は同研究所資源開発部門で管理. |
| 昭和53年 6月 (1978) |
富山医科薬科大学附置和漢薬研究所設置〔富山大学から移行〕 |
| 昭和55年 4月 (1980) |
富山医科薬科大学附置和漢薬研究所内に生薬資料室を設置. 生薬標本等を富山大学から移動,同研究所資源開発部門で管理. |
| 昭和60年 7月 (1985) |
薬学研究資料館の一階に民族薬物資料館を設置(202㎡), 生薬標本等を和漢薬研究所から移動. 同研究所資源開発部門で管理. |
| 平成 6年 9月 (1994) |
民族薬物資料館の増築(193㎡). |
| 平成 8年 5月 (1996) |
富山医科薬科大学和漢薬研究所附属薬効解析センター設置 (助教授1,助手1). 薬効解析センター運営委員会発足.民族薬物資料館の管理運営は同センターに移行. |
| 平成10年 4月 (1998) |
薬効解析センターに外国人客員教授,助教授の増員(各1). |
| 平成10年10月 (1998) |
第1回富山医科薬科大学民族薬物資料館一般公開.(この年から年1回開催). |
| 平成12年 4月 (2000) |
民族薬物データベースの公開開始. |
| 平成14年 4月 (2002) |
薬効解析センター民族薬物資料館学術標本利用規程他を施行. |
| 平成17年 7月 (2005) |
民族薬物データベース英語版の公開開始. |
| 平成17年 8月 (2005) |
附属薬効解析センターは附属民族薬物研究センターに改組され, 民族薬物資料館は同センターに所属する. 民族薬物研究センター民族薬物資料館学術標本利用規程他を施行. |
| 平成17年10月 (2005) |
富山大学和漢医薬学総合研究所附属民族薬物研究センター民族薬物資料館となる. |
| 平成19年3月 (2008) |
中国薬草古典「証類本草」データべースの公開開始. |
| 平成22年 6月 (2010) |
民族薬物資料館の完成記念式. |
| 平成23年11月 (2011) |
民族薬物資料館3階の改修工事完了. |
| 平成30年12月 (2018) |
民族薬物資料館所蔵の標本が30,000点を超える. |
| 令和2年4月 (2020) |
富山大学和漢医薬学総合研究所附属民族薬物資料館となる. |
建物


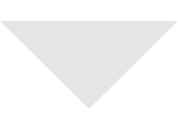

2010年6月新館完成
資料館保有資料には生薬標本のほか、植物標本(約33,000点)、生薬製剤、配置薬資料、本草書及び医方書などがあります。
展示室1
漢方医学・中国医学で使用する和漢薬、日本の民間薬など東アジアを中心に使用する生薬や頻用漢方処方に配合される生薬などを展示。他にも昭和初期まで実際に使用されていた「製丸機」や日本薬局方第5版生薬標本などを展示。
展示室2
インド医学(アーユル・ヴェーダ)などで使用する生薬や南アジア・東南アジア・西アジアで使用する生薬を展示。他にもチベット医学タンカや「らんびき」などを展示。

